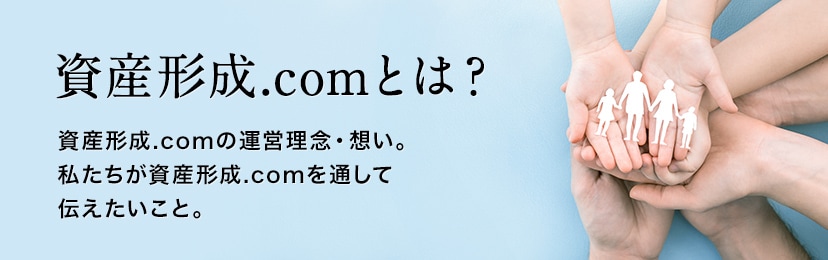金融リテラシーの向上について考えるにあたり一番考えなければならないこと、それは金融教育のあり方でしょう。日本と米国では大きな違いがあると言われている金融教育ですが、この金融教育の差が日本人と米国人の金融リテラシーの差にそのままつながっており、日本の預貯金の多さにつながっていると言っても過言ではありません。
そこでFPの目線から考える金融教育とは?また、これから金融リテラシーを向上させていくにはどうすればよいのか?ということについて、考えてみました。
参考記事:【FP目線で考える】なぜ日本は金利が上がらないのか?
大学時代に学んだ金融基礎知識、FPから見る金融教育とは?
私が大学生の時に最も感動した講義は、専門分野の授業でも語学の授業でもなく、証券会社と銀行の担当の方に毎週お越しいただき、講義をしていただいた『実務家による金融基礎知識』という講義でした。当時の私は、もちろん金融知識の欠片もなく、就職先は銀行に決まっていたものの、普通預金と定期預金の違いすらわからない学生でした。
だからこそ、このような実務的で社会人になるに当たり最も必要であろう金融知識を直接金融機関の方から教えていただける講義はすごく刺激的だったのを覚えています。もちろん就職活動をする前に自分で学べ!という声も聞こえてきそうではありますが、当時の私は教育学部であり経済学などとは無縁の生活を送ってきたことや、就職活動のことで頭がいっぱいで、結果的に銀行に就職が決まったというだけでした。
この講義を受講しても卒業単位には一切関係ないにもかかわらず、満席に近いくらい席が埋まっていたのは、学生の興味の表れでもあったのでしょう。興味がないわけではないのです。むしろ興味はあるのに、そういう場が提供されていなかったというのが日本の教育現場における実情です。
「経済学」と「金融知識」は別物
小学校や中学校では経済の基礎について、高校では少し専門的に、大学ではより専門的に「経済学」を学ぶことはできますが、残念ながら社会人になって最も必要であるはずの社会保障制度や税制、金融知識について詳しく学ぶ機会は用意されていません。
「経済学」で学ぶ需要と供給の話や、経済指標などの話が全く関係ないというわけではないのですが、残念ながらそのような知識を得ても投資はうまくなりませんし、もし「経済学」を学んだ人はしっかりとした金融リテラシーがあるということであれば、日本はこのような現状になってはいないはずです。
誰が金融知識を教えてくれるのか?誰も教えてくれないのが日本なのです。
知っているか、知らないかの差が大きな差
知っているか、知らないかというだけで大きな差が出てくるものです。
例えば企業に勤めて、その企業に確定拠出年金制度が導入されていたとしましょう。何もわからない状況で商品ラインナップを眺めるのと、しっかりとした知識がある状態で眺めるのでは、選ぶ商品も変わってくるはずです。
例えば、社会保障制度についても知っていれば申請できるものもたくさんありますが、あくまでも権利ですので、申請しないと何も起きません。知らないだけで損をしているケースは探せばたくさん出てくるはずです。
社会人になって必要になる知識は学校にて学ぶことができる、そんな環境でないといきなり放り出されてもチンプンカンプンです。仕事も忙しいし・・・ということになり結局何も知らないまま、場合によっては損をしながら生きていくことになってしまうのです。
金融リテラシーを向上させるためには?
私が思う金融リテラシーの向上とは、「金融関連のことについて自分で判断できるようになること」です。もちろん様々な制度や商品がありますので、全てを自分で判断できるようになるということは難しいと思います。
ですが、まずは自分のお金のこと、将来のことをしっかりと自分で考えることができるようになること、それが私の金融教育のゴールと考えています。
ではどうすればよいのか、選択肢は二択です。自分で学ぶか、誰かに教えてもらうかです。
ファイナンシャルプランニング技能士の資格を目指してみる
自分で学ぶ意欲のある方は、ぜひファイナンシャルプランニング技能士(FP技能士)の資格を受験してみるとよいでしょう。金融リテラシーの向上を目指すのであれば3級で十分です。1級はFP業務を生業としている方でも保有していないケースも散見されますので、まずは3級を目指してみてはいかがでしょうか?
本屋さんでテキストを購入し読むだけでもよいかもしれません。試験に合格したからと言って、投資がうまくなるということはありませんが、少なくとも基礎知識の習得はできるはずです。
プロからしっかりと学ぶ!金融リテラシー向上の近道
もう一つはプロの人に教えてもらうという方法です。受験には予備校があるように、家電量販店で店員さんが説明をしてくれるように、わからないことはプロの人に聞くのが一番です。
ポイントは6分野(ライフプランニング、保険、証券、税金、不動産、相続)全ての相談をできるプロであること、だと思います。一部分のみ相談ができても、他の部分との兼ね合いでその選択が正しかったかどうかの判断ができません。
全ての分野に精通している担当を見つけるというのはなかなか難しいかもしれませんが、お腹や頭が痛いときにかかりつけ医に行くように、何かあったときに相談できるファイナンシャルプランナーを探してみるのは良いことだと思います。
まとめ
金融教育の在り方と金融リテラシーの向上について、私の経験談を含め、思ったことを書いてきました。
日本の金融教育の在り方を理解し、少しずつで構いません。ぜひみなさんもご自身で金融リテラシーの向上に努めてみてはいかがでしょうか?