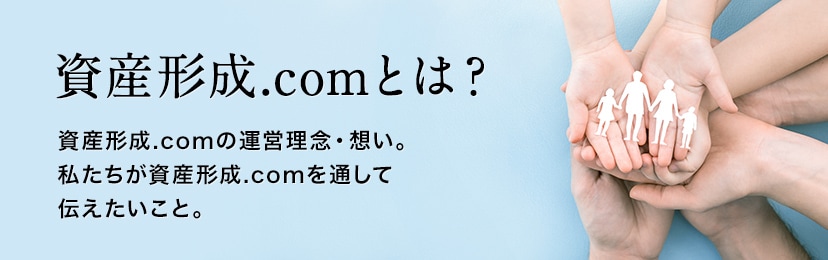投資信託にはチェックすべき2つの価格が存在します。
それは「基準価額」と「個別元本」です。
少し難しい用語のように思えますが、投資信託を理解する上で実務的にも非常に大事なポイントとなります。
本日はその「基準価額」と「個別元本」について解説をしていきますが、投資信託の基本となりますのでぜひ押さえましょう。
投資信託の基準価額とは?
基準価額とはわかりやすく言うと投資信託の現在の値段を示しており、株式でいうならば株価のことです。
投資信託は1口、2口といったように「口」という単位を用いて、「1万口あたり○○円」という形で値段を表示します。
例えば、ある投資信託が基準価額12,000円と表示されている場合、1万口あたり12,000円ということです。
これは1口あたりに直せば1.2円(=12,000円÷10,000口)ということになります。
上場株式の場合は市場が開いている時間帯は時々刻々と株価は変動していますが、株価とは違って1日に1つの価額として更新、反映されます。
投資信託の基準価額はどういう時に上がる?

投資信託の基準価額は日々値動きをしています。上がる日もあれば、下がる日もあります。
どういう時に基準価額が上がるのかというと、組み入れられているもの(株式や債券など)が値上がりした時は、その投資信託の基準価額も値上がりします。逆に、組み入れられているものが値下がりした時は、一緒に値下がりします。
基準価額は高い方がいい?安い方がいい?
基準価額は、組み入れられているものと共に値上がりするものでした。
では、基準価額が値上がりしているものを購入するのがよいのでしょうか?
そう結論付けるのは早計かもしれません。
基準価額が高いということは、今まで価格が値上がりしてきた投資信託といえます。運用結果もよく一見よさそうに見えますが、すでに割高のものが組み入れられている可能性もありますし、あくまでも過去の結果です。
逆に基準価額が安いものは割安でよいという考えも早計です。安いということは、あくまでも過去の結果ではありますが、今まで運用が上手く行っていなかった可能性もあります。
要は、組み入れられているものがこれから値上がりするかという事が最も大事で、基準価額が高いか安いかは、投資信託を選ぶ上で1つの指標にはなりますが、それだけで判断することはおすすめできません。
投資信託の個別元本とは?
基準価額と一緒に知っておくべきなのが、個別元本です。
個別元本とは、わかりやすく言うと取得単価のことです。つまり、投資信託を購入した時の基準価額になります。ただし、同じ投資信託を複数回購入した場合は、口数に応じて加重平均された値段になります。
投資信託の個別元本の計算方法

例えば、ある投資信託を基準価格10,000円で100口購入したとしましょう。この時の個別元本は、購入したときの基準価額になるため10,000円になります。
その後、基準価額12,000円で60口を購入したとしましょう。すると個別元本の計算式は以下のように、
(10,000円×100口+12,000円×60口)÷160口=10,750円
となり個別元本は購入単価である10,750円になります。
また個別元本は追加購入時以外にも、分配金がどのような形で分配されたかによっても変わってきます。
基準価額と個別元本の関係とは?
では、これら2つの投資信託の値段にはどのような関係があるのかを見ていきましょう。
個別元本は取得単価ですので、以下の関係が成り立ちます。
「個別元本<売却時の基準価額→利益」
「個別元本>売却時の基準価額→損失」
上記のように、基本的には売却時の基準価額が個別元本よりも上回っているか、下回っているかは、利益の計算をする上で非常に大切ですので、覚えておきましょう。
まとめ

「基準価額」は、投資信託の現在の値段、「個別元本」は取得単価となります。
これらは実際に投資信託を購入する際に、わかりにくい仕組みである一方で非常に大事な値段となってきます。
投資を始める前にしっかりと理解し、実際に投資信託の取引をする際にはこの点を重々注意して取引を行いましょう。