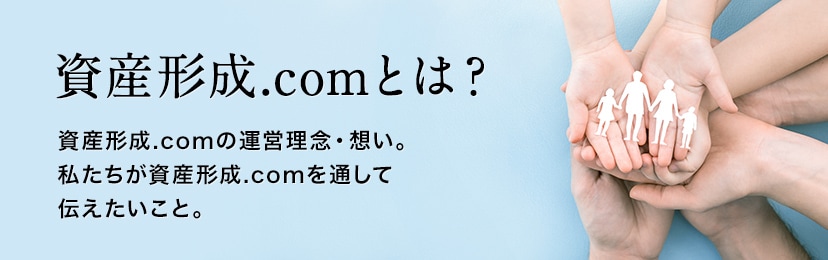資産形成や資産運用を行う上で株式投資の基本を押さえておくことは必要でしょう。
そして株式銘柄を選択する際に重要性が高まっている指標に、「ROE(自己資本利益率)」があります。
そこで今回はROEの基本や計算式、またなぜROEが株式投資において重要な指標についてお話していきます。
当記事を読むことで、投資におけるROEの使い方が理解かつ実践いただけると思いますので、最後までお付き合いください。
「ROE(自己資本利益率)」とは〜定義と計算式〜

まずはROEの定義から解説していきます。
ROEとは”Return On Equity”の略で、日本語では「自己資本利益率」あるいは「株主資本利益率」と訳されています。
自己資本(株主資本)(※1)に対する当期純利益(※2)の割合のことで、企業の収益性を測る指標の一つです。
※1 自己資本(株主資本)とは、企業の財務諸表(決算書)の一つである貸借対照表(B/S)(※3)上の「純資産の部」から少数株主持分および新株予約権等を除去した金額のこと。
※2 当期純利益とは、企業の財務諸表(決算書)の一つである損益計算書(P/L)(※4)における企業の一事業年度の売上とその他の収入からすべての費用や損失さらに税金を差し引いて最終的に残った利益のこと。
※3 貸借対照表(B/S)とは、企業の期末における財政状態(資産・負債・純資産の状態)を示す財務諸表(決算書)のこと。”Balance Sheet(バランスシート)”、略してB/S。
貸借対照表(B/S)
一定期間における資産、負債、純資産の状態を表す表で以下の図を参照。

損益計算書(P/L)
一定期間における収益、費用の状態を表す表で以下の図を参照。

ROE(自己資本利益率)〜B/S、P/Lとの関係〜

上図に基づいたROEの計算式は以下のとおりになります。
ROE(自己資本利益率)の計算式

たとえばA社の当期純利益が1億円、自己資本が10億円だとすると、ROE(自己資本利益率)は10%(=1億円/10億円×100)です。
ROE(自己資本利益率)が株式投資において重要な指標とされる理由

それでは、なぜこのROEが株式投資において注目を集め、重要な指標とされているのでしょうか?
その理由を端的に表すと、ROEが自己資本というその企業の株式に投資した皆さん(株主)の持分に対してどのくらいの利益(儲け)を出したかを表しており、その企業の経営者にとっては企業運営の成績表といえるものだからです。
たとえばB社のROEが1%、現在の銀行預金の金利が年2%だとしましょう。
この場合、投資家がB社株に投資した資金(株主持分)を1年間、B社の経営者が企業運営した結果、最終的に出せた利益(儲け)が1%ということです。
一方で株主持分を1年間、銀行預金に置いておけばB社は2%分の利子が受け取れます。
これでは、皆さんにとってもわざわざB社株にリスクをとって投資するよりも、その資金を銀行預金に置いておくほうが良いとなってしまいますよね。
つまり、このB社の経営者は非常に資本効率(※5)の悪い企業運営をしていることになり、一般的にはB社の株価は下落する可能性が高いといえるでしょう。
※5 調達した資本の運用効率のこと。
これは極端な例ではありますが、通常ROEが高ければ高いほど、その会社は資本効率の良い企業運営をしていることになり、株価は上昇する可能性が高いはずです。
一方でROEが低ければ低いほど、その会社は資本効率の悪い企業運営をしていることになり、株価は下落する可能性が高いといえます。
このように、ROEがその企業の資本効率の良し悪しを判断する指標だからこそ、投資の神様と呼ばれる世界的に著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏もこのROEに着目して株式投資を行っているのでしょう。
ただ、ここで一点注意すべきところがあります。
それは、ROEを構成する自己資本と当期純利益どちらがどのように増減しているかを見ておく必要があるということです。
たとえばA社の当期純利益が1億円、自己資本が10億円である場合、ROEは10%(=1億円/10億円×100)です。
それでは1年後にA社の当期純利益が2億円になり、自己資本は10億円のままだとしたら、ROEは何%でしょうか?
この場合、ROEは20%(=2億円/10億円×100)となります。
それでは1年後にA社の当期純利益は1億円のままで、自己資本が自社株買い(※7)して消却した結果5億円になったとしたら、ROEは何%でしょうか?
この場合も先ほどと同様、ROEは20%(=1億円/5億円×100)となりますね。
お分かりでしょうか?
その企業の経営者サイドにとっては、ROEを高める手段として利益(儲け)を増やす以外に、自己資本を減らすことができるということです。
しかし同じようにROEが高くなっても、利益(儲け)を増やした場合と自己資本を減らした場合で株価に対する影響は同じではありません。
一般的に、自己資本を減らした場合では短期的な株価上昇の要因になっても、利益(儲け)を増やした場合と異なり長期的な株価上昇の要因とはならない場合が多いです。
この点は誤りやすいところですので、十分注意していただければと思います。