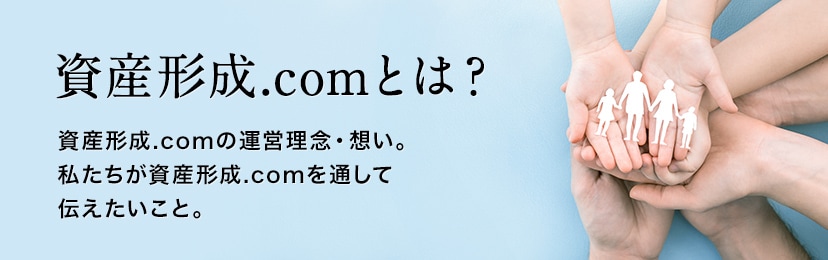20〜40代の投資初心者の方にとって用語一つとっても難しく感じてしまいがちな投資信託。
そこでここでは基準価額や分配金など初心者の皆さんにこれだけは押さえておいてほしい8つの基本用語を、できるだけ簡単にわかりやすく説明していきます。
基準価額、分配金・・・投資初心者向け投資信託8つの基本用語

投資初心者の皆さんが、投資信託を始める前に必ず押さえておきたい8つの基本用語について、ここから一つずつお話ししていきましょう。
基準価額(きじゅんかがく)
基準価額とは投資信託の値段です。
投資信託は1口、2口といったように「口」という単位を用いて、「〜口あたり○円」という形で値段を表示します。
大半の投資信託は「1万口あたり○○円」と表示されています。
例えば、ある投資信託が基準価額12,000円と表示されている場合、1万口あたり12,000円ということです。
これは1口あたりに直せば1.2円(=12,000円÷10,000口)ということになります。
実際には別途支払う購入手数料等を考慮する必要がありますが、これを一旦横に置いて単純化すれば、「購入時の基準価額<売却時の基準価額→利益」、「購入時の基準価額>売却時の基準価額→損失」という関係が成り立ちます。
分配金(ぶんぱいきん)
投資信託は一定期間ごとに決算(一定期間における損益額を計算すること)があります。
決算を行うタイミングや頻度は、あらかじめ投資信託ごとに決められており、一般的には毎月、半年ごと、1年ごとという3パターンに分けられることが多いです。
それぞれの投資信託における決算の際に、運用者の判断によってその投資信託の保有者(一般に「受益者」と呼びます)へ運用資金を還元することがあり、この受益者へ還元される運用資金を分配金といいます。
ここで初心者の方が誤解しやすい点があります。
それは投資信託の分配金と預貯金、あるいは債券の利子とを混同してしまうことです。
預貯金や債券の利子は投資元本とは別に一定額が支払われます。
例えば投資元本が100万円で年に1万円の利子が支払われる債券の場合、利子1万円が支払われた後も投資元本は100万円のままです。
一方で、投資信託の分配金は投資元本から支払われます。
上記の例に合わせて、投資元本が100万円、年に1万円の分配金が支払われる投資信託の場合で考えてみると、分配金1万円が支払われた後の投資元本は99万円(=100万円-1万円)ということになります。
投資信託は先ほどお伝えした基準価額が毎営業日ごとに変動しますので、実際にはこの投資元本と分配金の関係性が見えづらくなっています。
ですので、当該分配金の仕組みをあらかじめ理解しておきましょう。
投資対象資産(とうしたいしょうしさん)

投資対象資産とはその名の通り、受益者から預かった資金で投資する対象資産のことです。
例えば、投資対象資産が「日本株」となっていれば、その投資信託が日本国内の株式に投資するものであることがわかります。
ちなみにこの投資対象資産が一つの投資信託において「国内株」、「外国株」、「国内債券」、「外国債券」といったように、複数としている投資信託もあります。
信託期間(しんたくきかん)
信託期間とは投資信託の運用期間のことです。
たとえば、「信託期間2030年4月30日まで」ということは、この投資信託の運用が終わるのが2030年4月30日であることを表しています。
特に10年超の超長期での運用を考えている方は、信託期間が10年以下の投資信託を選択してしまわないよう気をつけましょう。
ちなみに実際には多くの投資信託がこの信託期間を無期限にしています。
信託期間が無期限の場合、予め運用を終える日は決められていませんので、原則としては運用がずっと続いていきます。
購入手数料(こうにゅうてすうりょう)
購入手数料とは投資信託を購入する際にかかる手数料のことです。
ちなみにこの購入手数料がゼロであることをノーロードと呼びます。
信託報酬(しんたくほうしゅう)

信託報酬とは投資信託を運用・管理してもらうための経費として保有期間中支払い続ける必要のある費用です。
この信託報酬は運用管理費用と呼ぶこともあります。
信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく)
信託財産留保額とは投資信託を売却(解約)する際にかかる費用のことです。
ただし、実際にはこの信託財産留保額を不要としている投資信託が多くあります。
ファンドマネージャー
ファンドマネージャーとは受益者から預かった資金を実際に運用(指図)する者のことです。