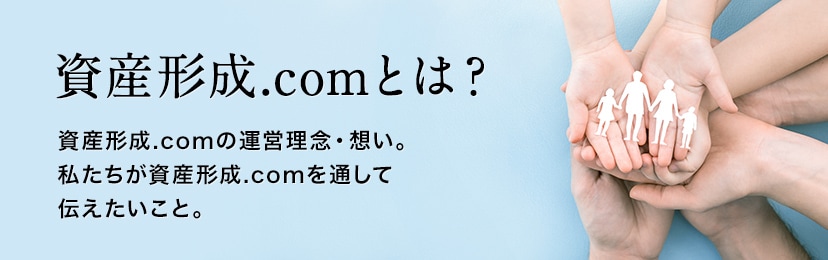今回はある初心者の方からいただいた、実際の相談を基に老後資金のための資産形成と資産運用について具体的に見ていきましょう。
参考記事:あなたは誰に相談しますか?資産形成の相談をする時の注意点とは?
相談に訪れた資産運用初心者(30歳男性)の相談内容について考える!
ある日、弊社主催の資産運用セミナーを受講した後に「後日個別に相談したいことがあります。」とおっしゃっていた30歳男性の方がご来社されました。
彼が”個別に相談したい”とおっしゃっていた相談内容はこうです。
「先日のセミナーをお聞きしただけでなく、資産形成.comをはじめ色々なサイトや本などで自分なりに調べたりしましたが、やはり老後資金を今のうちから地道に準備しておくことが大事だと思いました。
現在は収入の一部をコツコツ貯めた100万円を銀行の普通預金に置いています。どうせならお金に不自由することのない老後生活を送りたいので、会社を定年になる60歳までに1億円の資産をつくりたいと考えています。どのようにしていったらよいでしょうか?」
そこでもう少し詳しく現在の状況を知りたいとお伝えして、ヒアリングした内容が以下のとおりです。
相談内容:「老後資金として60歳までに1億円の資産をつくるには?」

上図にあるように職業は会社員、家族構成は独身の一人暮らし。
1年間の収支は年収が額面400万円、税金や社会保険料等を差し引くと手取りで300万円の一方、年支出は家賃等すべて込みで200万円。
また資産状況は資産が銀行の普通預金に100万円ある一方、借入金などの負債はないとのことでした。
ここで注目したいのは1年間の収支が100万円の黒字(=手取り年収入300万円-年支出200万円)である点です。
これが継続できる前提で考えれば、既に保有している銀行の普通預金100万円と併せて60歳までの30年間に3000万円(=資産100万円+100万円/年×29年)を貯蓄できます。
ただ、あくまでも目標は1億円ですから、これでは7000万円の不足(=3000万円-1億円)となってしまいます。
そこでこの年100万円ずつを銀行の普通預金に寝かせておくのではなく、毎年、株式や債券、投資信託といった金融商品に定額積立投資して、この不足分の7000万円をリスクを取ることによって得られる可能性のある資産の値上がり益、配当や利子収入で賄うことを考えます。
それでは年何%の運用利回りがあれば目標を達成することができるでしょうか?
ここでは複利(※3)で年2%、年4%、年6%、年8%、年10%、各々の運用利回りで試算してみました。
なお計算をわかりやすくするために手数料や税金といった実際の取引で掛かるコストは考慮していませんのでこの点は注意が必要です。
目標達成のための必要運用利回り:毎年定額積立投資の場合(1)

目標達成のための必要運用利回り:毎年定額積立投資の場合(2)

上図のように毎年定額積立投資を30年間に渡って行った場合を試算すると、運用利回りが年2%で4138万円、年4%で5833万円、年6%で8380万円、年8%で1億2235万円、年10%で1億8094万円という結果になります。
つまりこの試算結果から年8%以上の運用利回りを得られれば目標を達成することができるのが分かります。
さてそれでは年8%以上の運用利回りを目指すには・・・とここまでお話したところで相談者の彼から待ったが掛かりました。
相談者の方が話された内容は以下です。
「ここまでのお話はよく分かりました。ただ、年8%以上の運用利回りを目指すというのはとてもリスクが高くて怖いように思えてなりません。あくまでも私の勝手なイメージですが。もう少し堅実な運用利回りで目標の1億円に到達することはできませんか?」
年8%以上の運用利回りを目指すというのは決して非現実的なものではないですが、黒字額を収入増と節約による支出減などで1年間の収支の黒字額を、徐々に膨らませることができる前提であれば、以下のような方法も考えられます。
それは、先ほどのように毎年100万円ずつ定額積立投資するのではなく、当初100万円、以降毎年+10万円ずつ投資額を増やしていく逓増額積立投資です。
要するに毎年の投資額を1年目100万円、2年目110万円、3年目120万円、・・・、30年目390万円と増やしていくというわけです。
この場合、60歳までの30年間に7350万円(=100万円+110万円+120万円+・・・+390万円)を貯蓄することができます。
そうすると、目標の1億円までは2650万円の不足(=7350万円-1億円)となり、この不足分をリスクを取ることによって得られる可能性のある資産の値上がり益、配当や利子収入で賄えば良いことになります。
それではこの場合、年何%の運用利回りがあれば目標達成となるでしょうか?
先ほどと同様に複利で年2%、年4%、年6%、年8%、年10%、各々の運用利回りで試算してみました。
なお、ここでも計算をわかりやすくするために、手数料や税金といった実際の取引で掛かるコストは考慮していませんのでご注意ください。
目標達成のための必要運用利回り:毎年逓増額積立投資の場合(1)

目標達成のための必要運用利回り:毎年逓増額積立投資の場合(2)

上図のように逓増額積立投資を30年間に渡って行った場合を試算すると、運用利回りが年2%で9528万円、年4%で1億2615万円、年6%で1億7047万円、年8%で2億3478万円、年10%で3億2889万円という結果になります。
つまり、この試算結果から年4%以上の運用利回りを得られれば、目標を達成することができるのが分かります。
これであれば先ほどのちょうど半分で目標に到達しますから、だいぶ気が楽になったのではないでしょうか?
ただ、投資額を毎年10万円ずつ増やしていくというのは、そう簡単なものではありません。
何せ30代で年100万円台であった投資額が40代で年200万円台、50代にいたっては年300万円に上るわけですから。
そこで主軸に据えるのは、毎年の投資額を100万円ずつとする定額積立投資で運用利回り年8%以上を目指しつつ、無理のない範囲で投資額を徐々に増やしていってはどうかとお伝えしました。
上図の表を1行ずつ追っていただければお分かりいただけるかと思いますが、投資年数が早い投資資金は当然運用可能年数が長くなりますので、その分複利効果を得られやすいことになります。
また、資産形成を始めた初期の段階であれば、累積での投資金額がまだ少額で残りの運用可能年数が十分に長いです。
そのため高い利回りを狙ってリスクを高めに取ったことが仮に裏目に出て運用損が発生することがあっても挽回を図りやすいといえます。
これとは逆に50歳を過ぎて累積の投資金額が大きくなり、かつ残りの運用可能年数が10年を切った段階で、積極的にリスクを取りに行って運用損を抱えてしまった場合はどうでしょうか?
挽回は非常に難しくなるというのは容易に想像できるでしょう。
ここまでお話したところで、相談者の彼から「大枠の取り組み方は納得のいくもので理解できました。ご提示いただいた通りに実践してみようと思います。」との言葉をいただきました。
以上、相談者の話はここで終わりです。