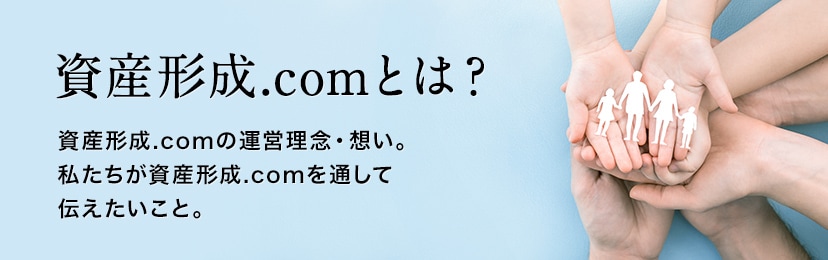結婚資金に教育資金、老後資金など、人生にはとにかくお金が必要です。
それらのライフイベントに合わせた資金を、どのように準備していますか?
銀行でコツコツ預金を貯めていても、気付いたら貯蓄分に手を付けてしまって、思うようにお金が貯まらないという経験をした方は多いはずです。
そこでおすすめしたいのが「貯蓄型保険」です。
保険で貯金ができるの?と疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、実は保険商品によっては貯蓄性が優れたものがあるのをご存じでしたか?
ということで当記事では貯蓄性が高い保険について説明します。
貯蓄型保険の仕組み
契約者が支払う保険料には、「純保険」と「付加保険料」があり、このうち「付加保険料」は、保険会社が事業を運営していくための経費に充てられます。
それに対し、実際に将来の保険金に充てられるのが「純保険」です。
貯蓄型保険では、この「純保険」は保障と貯蓄に充てられます。
保障に充てられた分は、被保険者が亡くなったり、高度障害状態になったときに死亡保険金として支払われ、万が一の時の保障となります。
一方、貯蓄分に充てられた保険料は、保険会社が積み立てて長期間にわたって運用するため、保険が満期を迎えたときには満期保険金が、解約したときには解約返戻金を受け取ることができるのです。
保険料を貯蓄分に回し、死亡時以外でも満期保険金や解約返戻金を受け取ることができる点が、掛け捨て保険との大きな違いとなっています。
このように保険でありながら、万が一の時の保障だけでなく、将来の資産形成もできることが貯蓄型生命保険の大きな特徴です。
貯蓄型保険のメリット・デメリット
保険に加入するにあたって、知っておくべきメリット・デメリットは何があるのでしょうか。
以下、解説していきます。
メリット
貯蓄型保険のメリットは何と言っても、支払った保険料が手元に戻ってくる点でしょう。
掛け捨て保険の場合は、万が一の時の死亡保険を受け取らない限りは、保険料が戻ってくることはありません。
しかし貯蓄型保険の場合は死亡保険金だけでなく、満期保険金や解約返戻金があり、いずれかの形で保険金を受け取れるのです。
貯蓄型保険の場合は先ほどもご説明した通り、保険料の一部を積み立てて運用しているため、貯蓄性が非常に高い保険といえます。
この保険は長期間での運用によって資金形成をしているので、資金準備に余裕があり、万が一の保障もほしいという若い世代の方に特におすすめです。
デメリット
貯蓄型保険は保険料に貯蓄分が組み込まれているため、貯蓄性が高いほど保険料が高くなる傾向があります。
また、この保険料は一般的に、定期保険・終身保険・養老保険の順に高くなります。
貯蓄性が優れていて万が一の保障も付くのですから、「どうせ契約するならば充実した内容で契約をしたい!」と思われるでしょう。
しかし、保険料も契約内容に伴って高くなるため、無理なく支払い続けられる保険料で設定するのがベターです。
契約の途中で解約もできますが、解約のタイミングによっては解約返戻金が、払込総額に対して元本割れすることもありますので、注意が必要です。
貯蓄型保険の種類
貯蓄型の保険には主に養老保険と終身保険があります。
それぞれの特徴と性質を学び、加入してから「こんなはずじゃなかった」と後悔のないようにしましょう。
養老保険
養老保険とは一定の保険期間を設定し、その期間内で死亡あるいは高度障害状態になった際には、死亡生命保険金を受け取れ、保険期間が満期を迎えたときには、満期保険金が受け取れる保険です。
万が一のとき、健康で満期を迎えたときとどちらの場合でも保険金を受け取れるのが、養老保険の大きな特徴といえます。
なお、死亡保険金も満期保険金も受け取れる保険金は同額です。
また、養老保険は非常に貯蓄性が高い保険ですので、保険料も高く設定されています。
途中で解約をした場合、解約返戻金を受け取ることもできますが、養老保険の場合、解約返戻金は元本割れのリスクがあります。
養老保険に加入する場合は、満期まで契約を継続することを前提として契約するようにしましょう。
養老保険の注意点
ところで非常に貯蓄性が高く、保険金を受け取ることができる養老保険ですが、注意するべきポイントがあります。
それは、養老保険の多くの場合、受け取ることのできる保険料は、払い込んだ保険料を下回るということです。
保険会社は集めた保険料を運用して利益を出し、得た利益を保険者に還元します。
かつては金利が高く、預貯金よりも貯蓄性が高いと人気がありましたが、近年は低金利が続き、その運用実績によってはリターンが期待できないこともあります。
これらの運用利益と、支払った保険料から保険会社の経費を引くと、実際に受け取る保険金は払込総額よりも低くなることがあるのです。
こう聞くと、受け取れる保険金が少なくなってしまうなら、銀行の預金のほうが利息もつくし、確実に貯蓄できるのではと思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、養老保険は貯蓄目的で加入する方が多いとはいえ、あくまでも保険商品なのです。
例えば20年間に渡って毎月、一万円の保険料を払う、あるいは銀行に預金として入金した場合を例にあげてみます。
養老保険の場合、保険料の総額は20年間で240万円(1万円×12ヶ月×20年間)になりますが、運用実績によっては受け取れる満期保険金は240万円より少ない可能性があります。
預金であれば、20年分の入金分である240万円が元本割れすることはなく、240万円+利息を受け取ることができるということです。
つまり、銀行にコツコツと預金したほうが、20年後に手にする資金は大きくなります。
ところが、途中の10年目に被保険者に万が一のことが起きた場合、養老保険に加入していれば、満期分の保険金を受け取ることができますが、預金の場合は、予定していた半分の額しか貯蓄できていません。
養老保険は万が一の場合の保障をしつつ、資金を形成するという性質を持った保険です。
その特性を理解したうえで、あなたにとって養老保険に入るメリットとデメリットのどちらが大きいのか判断して加入を検討しましょう。
終身保険
終身保険は保障が一生涯続きますので、「満期」という概念はありません。
そのため、終身保険で資金を得ようと思うと、死亡時に家族に保険金を残す方法と、契約の途中で解約して解約返戻金を受け取る方法があります。
このように、死亡時に保険金を受け取れる特長を活かして、被保険者が亡くなった後の葬儀費用や相続税対策として加入している方もいます。
一方、早期に解約して子供の教育資金や夫婦の老後資金など、資金形成を目的とすることも可能です。
また終身保険は、長期にわたって保険料を運用することができるため、一定期間を経過すると解約返戻金が払込総額を上回ります。
しかし、解約返戻金は解約のタイミングによっては元本割れすることがありますので、注意が必要です。
なお、終身保険で設定されている保険料は、平均寿命が長い女性のほうが男性よりも安く設定されていることも特徴です。
まとめ
以上、貯蓄型保険が、貯金代わりになることはご理解いただけたでしょうか。
銀行の預金では、簡単にお金を引き出せる利便性ゆえに、しっかりした意志がないと長期間にわたって定期的な貯蓄をしていくことは難しいという側面があります。
それに対して保険商品であれば、毎月保険料が引き落とされるため、半ば強制的に資金を確保することができるのです。
また保険には万が一の保障もあるため、銀行の預金ではカバーできない不測の事態に備えることもできます。
もちろん人によっては、銀行預金のほうがライフスタイルに合っていると感じる方もいるでしょう。
しかし、自力での貯蓄が苦手で、確実に貯蓄できる方法を模索している方には、保険での貯蓄は貯蓄の確実性という点で分があります。
今後「貯蓄」を考えたときには、ぜひ保険商品という選択肢も加えてみてください。
またご自身のライフスタイルにおいて、何があっているのかが判断難しい場合、金融のプロであるファイナンシャルプランナーに相談してみるのも良いでしょう。